佐藤工務店モデルの 佐藤氏セミナー コラム 「性能のその先へ」

佐藤工務店 佐藤氏セミナー「性能のその先へ」
本セミナーは、2025年春の省エネ義務化決定を背景に、「省エネだけでは差別化できない」という問題意識から、デザインの重要性に焦点を当てて開催されました。高性能化が当たり前となった今、工務店が生き残るためには、異なる強み、特にデザインの力を活用することが求められています。
自己紹介と事業内容
佐藤工務店は、新潟県三条市を拠点とする設計施工の工務店で、主に住宅を手掛けています。
- 主な事業: 住宅の設計施工、リフォーム、リノベーション。近年は省エネ性能を高め、太陽光パネルを搭載し、持続可能な素材を用いたエコハウスを中心としています。
- B2B事業(同業他社サポート): 構造計算の受託、断熱・施工のアドバイス、気密測定、大型パネル施工のサポートなどを全国の工務店や設計事務所向けに行っています。
- 非住宅事業: 木造の平屋オフィス、倉庫、中規模非住宅のサポート、島根県の離島での住宅供給プロジェクト、災害被災地への住宅供給支援など、多岐にわたる案件を手掛けています。これらの多くで大型パネル工法が採用されています。
- コミュニティ活動: 大型パネルのユーザー会である「みんなの会」の会長、新潟県中心の「住学」コミュニティの立ち上げに関わっています。
高性能化の「その先」としてのデザイン
現在、耐震等級3、断熱等級7への対応は多くの工務店で可能となり、高性能はもはや「当たり前」の時代に突入しています。これにより、高性能を謳うだけでは差別化が難しくなってきました。
デザインの成長力・集客力・ブランディング効果
デザインは数値で評価しにくい分野ですが、佐藤氏の事例からその効果が数値として現れています。
- 成長力: 手掛けたオフィス(約70㎡)では、完成後2年間で売上が130%に伸び、従業員が4倍になりました。求人に苦労していた会社でしたが、建物をホームページに掲載したところ、応募が増加しました。別の倉庫兼事務所(155㎡)でも2年で売上が130%を達成し、リクルート効果が高まりました。
- 集客力・ブランディング:
- 大阪万博の「世界最大級の木造建築」は、デザインの力でリピーターが続出するほどの集客力を持っています。
- 共催企業であるシネジック社の木造デザインの社屋は、多くの方が見学に訪れ、建物自体が企業のブランディングに繋がっています。
- 建物に投資し、デザインを重視することは、企業や製品のブランドイメージを高める効果があります。
「意味のあるデザイン」の重要性
一般に「おしゃれな家」が求められますが、服のように数年で変えられない住宅は、トレンドを取り入れるのではなく、スタンダードでトラディショナル(伝統的)で持続可能なデザインが良いとされます。
ルールとディテールが生む希少性
みんなと同じベーシックなデザインの中で希少性を生むためには、デザインの基本ルールを理解し、ディテール(細部)を丁寧にデザインすることが重要です。
デザインはセンスや奇抜さではなく、ちゃんとした理由とルールに基づいて行えば、誰でも優れたデザインを実現できると考えられます。
敷地条件・問題を解決した結果としてのデザイン
優れたデザインとは、敷地の立地条件や施主の要望など、個々の問題を解決した結果として生まれる形であるべきです。
- 事例1(新潟の分譲地):
- アルミカーポートを推奨しない街並み規制に対応するため、木造で乗降時に濡れないように大きな庇を計画。
- エコハウスとして南に大きな屋根(下屋)を設けて発電。
- 北側の隣地に日影を落とさないよう、上屋の屋根を北側に下げる「ハの字型」のデザインを採用。
- 形は「好き嫌い」ではなく、「解決すべき理由」の結果として成立しています。
- 事例2(交差点の建物):
- 交差点の見切り(見通し)を確保するため、1階に壁を設けず、2階を持ち出しにしたビルトインカーポートを採用。事故防止への配慮がデザインに反映されています。
- 事例3(桜並木の北側リビング):
- 道路を挟んだ桜並木を望むために北側に大きな開口部を設置。
- 見物人からの視線を遮るため、バルコニーを1.82m持ち出し(出幅一軒)にし、視線カットを実現。
- 夏場の西日を避けるための壁の設置も施し、快適性を確保しています。
構造・機能とデザインの関係
デザインは、構造や機能といった骨格部分の上に成り立つべきです。構造がしっかりしていれば、デザインは自ずと美しくなります。
構造のルール
- 直下率(ちょっかりつ)が高い構造(1階と2階の柱の位置が揃っている状態)を優先することで、力の流れがスムーズになり、窓も整然と配置でき、外観・内観ともに美しいデザインに繋がります。直下率が低い(柱がずれる)と、大きな梁が必要となり、不安定な構造になるだけでなく、窓の位置が不揃いになりデザイン的にも劣ります。
- 大手ハウスメーカーの一部事例では、直下率が50%~58%程度のものも見受けられ、構造への配慮が不足しているケースがあります。
- 力の流れが素直な建物は、自然と美しいデザインになります。
安全性への配慮とデザイン
安全性や持続性能を高めることも、デザインを損なうことではありません。
- 段差の解消: 危険な段差をなくすことで、手すりなどの後付けの安全対策が不要になり、よりシンプルなデザインを維持できます。
- 滑り止め: 階段の木のスリットは滑り止めとして不十分であり、ゴム製の埋め込み滑り止め(アシスト社製など)の方が安全性が高く、デザインを損ないません。
- ストリップ階段(スケルトン階段): デザイン性を優先してスケルトンにしても、手すりや蹴込み板の隙間を10cm以内にすることで、子供の落下を防ぐ安全性を確保できます。
デザインと機能の優先順位
デザインは、機能(構造・安全・性能など)の充足があってこそ意味を持ちます。
- 機能優先: まず機能を満たす。
- 結果としてのデザイン: その結果として、意味と理由のあるデザインが生まれる。
デザイン先行で考えると、機能しない、持続しない、一過性のデザインになってしまいがちです。機能優先で生まれたデザインこそが、長く価値を保ち続ける持続可能なデザインとなります。
デザインのテクニックとNG事例
テクニック:水平ラインと屋根勾配
- 低く構えた水平ライン: 建物の高さを低く抑え、水平のラインを強調し、奥行きを出すことで、外観を美しく見せます。図面で見るよりも、実際に現場では建物は高く見えるため、標準よりも低く作るなどの調整が必要です。
- 屋根勾配: どの位置から建物を見るかという立地条件を考慮することで、最も美しく見える屋根勾配が決まります。本屋と下屋の角度は、見る場所によって異なる角度にすべき場合があります。
NG事例:避けるべきこと
- トレンドの採用: 流行は必ず廃れるため、住宅のような長期間残るものにトレンドを積極的に取り入れると、数年後に「古いもの」になってしまいます。
- 構造を無視した間取り・外観: 構造のルール(直下率など)を無視してデザインを考えると、強度が不安定になるだけでなく、窓の位置が不揃いになるなど、デザイン的にも問題が生じます。
結びの言葉
今回の話を通して、デザインと構造や安全は対立するものではなく、むしろ構造がしっかりしていればデザインは必然的に美しくなるという考えを強調しました。デザインありきではなく、機能があってこそのデザインであり、それが持続するデザインに繋がります。
佐藤工務店からのお知らせ
- 同業者向けのサポートメニューとして「あっさりサポート(相談ベース)」、「こってりサポート(勉強会・スキルアップ)」、気密測定、構造計算の受託などがあります。
- 本セミナーで語られた構造とデザインに関する内容は、出版されている書籍にも詳しく解説されています。
暮らしとともにしつらえていく楽しみ「ハーフ住宅」とは
ハーフ住宅は、高品質の骨格と外装、水道、電気、ガスと、法律的には住宅として最低限「暮らせる」状態でお施主さんに引き渡す住宅です。  世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。
世界の住宅の標準ともいえるスケルトンインフィル。
柱などの木が見えるむき出しの状態から、みずから中を自分好みにしつらえていく。
つまり、家を自由にデコレーションしていくことができる住宅です。
コンクリートの打ちっぱなし住宅の木バージョンともいえる「木の打ちっぱなし住宅」ともいえます。
High quality 高気密・高断熱・高耐震の高い品質
More than reasonable 価格を低く抑えられる
Do it yourself 自分色に仕上げられる
人気の一級建築士が設計した、これら3つのコンセプトを持った複数のプランの中からお選びいただけます。
コストを抑えながら高性能住宅が手に入る反面、お施主さんにも「しつらえる覚悟」を持ってもらう必要があります。
なので「内装まで全て出来上がった状態の住宅が欲しい」「できるだけ自分で手を加えたくない」という方には正直オススメできません。
逆に、「自分好みに自由に作ってみたい!」「ちょっとぐらい不格好でも逆に私らしさが出ていいかも!」 「高気密・高断熱・高耐震で建てたい!でも、できるだけコストを抑えたい!」
そんな方にピッタリです!
「ハーフ住宅」を、ぜひ夢のマイホームの選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか? 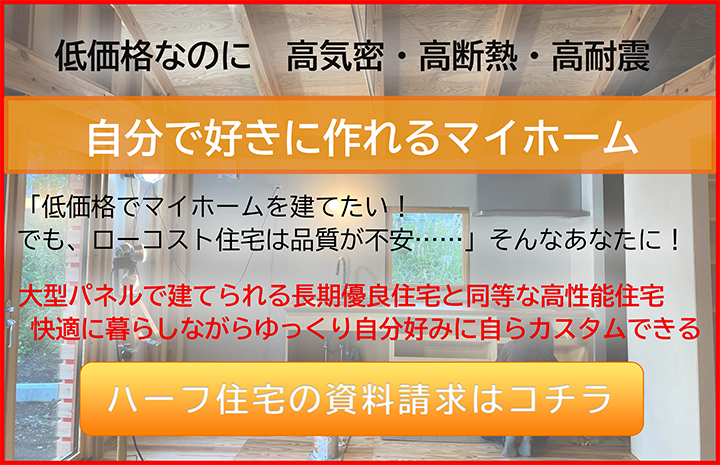





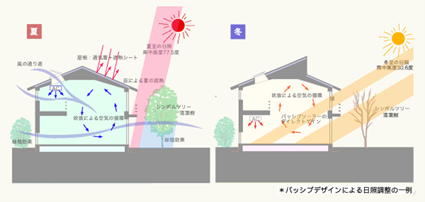



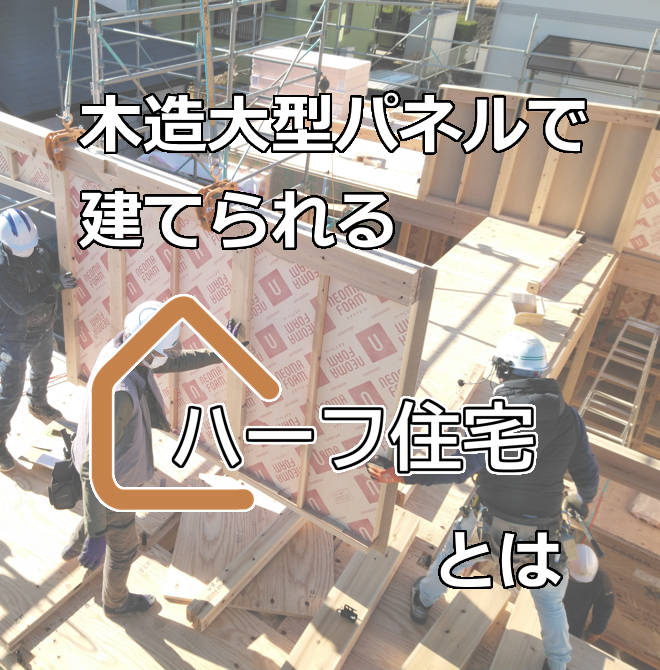
この記事へのコメントはありません。